大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器・免疫内科学
Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, The University of Osaka
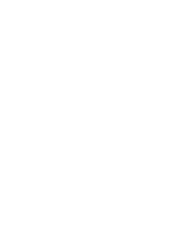
佐多愛彦
肺癆科教授
在任期間:明治38年~大正13年
佐多愛彦は明治4年鹿児島市に生まれた。鹿児島医学校から東京大学医学部撰科に進んで外科学及び病理学を専攻する。明治27年1月、そのころ富山市立病院に勤務していた佐多は府立大阪医学校の校長だった清野勇からの誘いで大阪の地を踏んだ。翌28年には24歳の若さで、大阪医学校で病理学と細菌学の両教室を設置して教授になった。明治30年大阪府の教授洋行制度の第一回生としてベルリン大学ウィルヒョウの下に留学し結核の病理について研鑽を積んだ。
赴任したときの府立大阪医学校は専門学校だったのだが、佐多は赴任するや「人命に尊卑なし。国民は平等に医療を受けられるべきであり、医療にあたる医師の育成は全国同レベルでなければならない」と主張した。これが有名な『医育統一論』で、医学教育には大学と専門学校の二級制機関があってはならぬと、文部省をはじめ各方面を説得し、医科大学の設置に奔走した。その熱意が大正4年、大阪府立高等医学校の大阪府立医科大学昇格となって実を結び、初代学長として大正13年まで活躍した。大阪府立医科大学は今日の阪大創設の礎となり、佐多愛彦が阪大創設の恩人とされる所以である。
また、佐多は明治35年、32歳で大阪府立医学校の校長兼病院長となったが、大学昇格をめざす一方で、明治38年5月、大阪に肺結核患者が多かった時勢を明察して全国に先駆けて内科の一角に「肺癆科」を新設した。肺癆とは、肺結核のことで、わが国で初めての肺結核専門講座であった。当時の結核死亡率は現在の癌による総死亡率とほぼ同じくらいであり、若くして感染死亡に至り、不治の病とされ非常に恐れられた病気である。

当時は結核に対して有効な治療法はなかったが、大阪の富豪竹尾治右衛門の寄付を得て「竹尾結核研究所」を佐多愛彦所長のもと大正6年開所した。竹尾結核研究所は「肺癆科」とともに結核撲滅の支持組織として先駆的役割を果たした。竹尾結核研究所は後に阪大微生物病研究所の核となる。
大正6年の火事による大学病院消失後、不燃の新病院完成を機に佐多は大正13年に54歳で引退する。日独協会を創始。昭和5年第8回日本医学会会頭。肺癆における混合感染の論文が顕著である。昭和25年3月4日、80歳で逝去。佐多愛彦胸像(新海竹蔵作)は現在の大阪大学医学部正面にある。
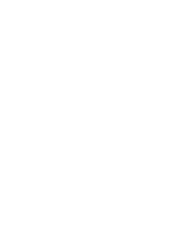
今村荒男
第三内科 初代教授
在任期間:大正14年~昭和23年
今村荒男は明治20年奈良法隆寺近くの安堵町に生まれた。鹿児島の旧制第七高校卒業後、大正元年東京帝国大学医学部卒業。東大青山内科に入局。
このころ、予防医学の必要を痛切に迫る深刻な状況が発生した。大正7年、スペイン風邪(流行性感冒)が大流行し、死者が39万人にものぼった。流感は翌8年も暴威をふるい、混合感染により結核の死亡者数は過去最高に達し、感染症の脅威がいちだんと強まった。このため大正8年に「結核予防法」が成立し、大正12年に「日本結核病学会」が発足した。14年には結核予防デーが実施されるなど、結核をはじめとした呼吸器系疾患への関心がかつてないほど高まった。このように、国民が結核の脅威に震えあがっていた大正14年、東大伝染病研究所で感染症の免疫を研究していた今村荒男が佐多の後任として着任する。この直後、肺癆科は第三内科と改称し、今村は第三内科初代教授となった。微生物病研究所の付属施設となった竹尾研の研究部長や微研所長を兼務したほか、昭和20年には新設の奈良県立医学専門学校(現奈良県立医科大学)の初代校長、結核予防会大阪府支部長などを引き受け、今村の元で第三内科は結核の診療と研究に全力を挙げた。診察ではカルテに五線譜を書き打診音の音程を記していたという。研究活動としては、結核予防の研究に懸命に取り組み、昭和2年の日本結核病学会総会で「結核ワクチンの予防的効力批判」と題して報告、結核の予防には結核免疫を利用すべきであると結論し、BCG接種が最も有望であると主張した。今村は昭和2年、パスツール研究所カルメット研究室で結核予防に関する研鑽を積み、帰国後本格的に研究に取り組んだ。まずBCGを乳幼児に飲ませたが、陽転反応が悪いので注射でなければと考え、初の人体接種を試み成功したことが認められ、昭和18年結核予防法にBCG接種が採用されることになった。レントゲン検診車を考案試作し集団検診車を初めて使用したのも阪大第三内科であり、集団検診とBCG接種は結核予防医学の中核として位置づけられることとなった。
今村は昭和21年に第5代大阪帝国大学総長になり、それまで医学部、理学部、工学部の理科系学部だけだった阪大に文学部、法学部、経済学部などの文科系学部を設置し、総合大学へ発展させた。容姿端正、英国紳士を絵に描いたような人だったが、門下生に対する指導は厳しく「雷を落とされた記憶のない者はいない」というほどで、妥協を許さず真摯に研究に向かう態度は、まさに碩学と呼ぶにふさわしい人であった。
昭和34年大阪府立成人病センター(現、大阪国際がんセンター)初代所長。昭和35年文化功労者。昭和38年第16回日本医学会総会会頭。昭和42年6月13日、81歳で逝去。
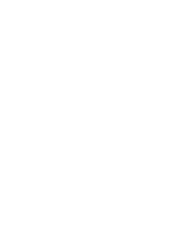
堂野前維摩郷
第三内科 第二代教授
在任期間:昭和23年~昭和36年
堂野前維摩郷(どうのまえいまさと)は明治31年和歌山県に生まれた。大正11年東京帝国大学医学部卒業、昭和16年千葉大学教授、昭和23年に大阪大学医学部教授、昭和27年大阪府立羽曳野病院(現、大阪はびきの医療センター)院長(兼任)。
堂野前は、東大稲田内科から昭和2年29歳の若さで千葉医大佐々内科の助教授として赴任し、昭和16年佐々先生の後任として教授へ着任した。昭和23年、今村が総長に就任し、その後任として第三内科の第二代教授となった。堂野前は循環器系統の臨床内科医だったが、結核研究に取り組んできた第三内科の実績と前任者今村の路線を尊重し、研究の主体を結核に置いた。当時、結核予防の研究はほぼ完了しており、結核治療に絶大な威力を発揮する抗生物質「ストレプトマイシン」の導入以降は次々に開発される抗結核剤の臨床評価の研究を精力的に実施した。このとき、第三内科関連結核療養所施設は十数カ所、病床数は5000床に近く、これらの施設の総力を挙げて新薬の臨床評価の研究を進め、化学療法の定着に貢献し、臨床医学の大家と呼ばれた。昭和31年には学研の結核化学療法研究班の班長となり、全国の結核臨床医学のリーダーとなった。この研究班の業績として「肺結核の学研分類及び病状経過判定基準」があり、これは現在も広く一般に採用されている。
もともと循環器の専門医だった堂野前は呼吸器疾患の臨床を通じて、心臓や肝臓など周辺臓器との関連性を求めて研究領域を広げ、胸部疾患全体へ研究領域を広げた。さらに気管支喘息などのアレルギー性疾患、当時臨床応用され始めた副腎皮質ホルモンの研究をめざし、肝臓代謝学研究室、内分泌アレルギー研究室などを誕生させ、肺癆科として始まった教室を、内科学全般を診療する教室へと展開させた。こうした環境下で教室員たちが切磋琢磨しあって有能な医局員が育っていった。
堂野前は温厚、高潔な人柄で医局員からは「大きい声でお叱りになったのを聞いたことはない。今村先生は全く対照的に話を半分も聞かれずに雷を落とした人で、それに慣れており、はじめはとまどった。」と言われていた。居丈高に門下生を叱責することはなく、自由にのびのびと研究させるという主義だったようである。また、堂野前内科は学生たちに格好よいと、とても人気があった。他の内科がやっていない免疫学や膠原病なども研究していて学生たちには興味深く、当時医局には100人ほど在籍していた。また、医局員を心服させたのは臨床医としての卓越した力量で、患者の診療にあたっては、つねに「注意深く観察し、適切に処置する」という原点を忘れなかった。昭和37年大阪府立病院(現、大阪急性期・総合医療センター)院長、昭和44年住友病院長。昭和50年12月8日、77歳で逝去。
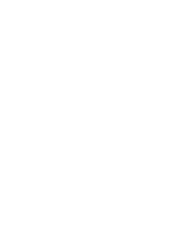
山村雄一
第三内科 第三代教授
在任期間:昭和37年~55年
山村雄一は大正7年大阪に生まれた。昭和16年大阪帝国大学医学部を卒業し、海軍軍医中尉、国立診療所刀根山病院内科医長(兼大阪市立医科大学助教授)のころ、結核性空洞の形成は結核菌成分に対する遅延型アレルギーであることを提唱した。米国留学を経て九州大学医学部生化学教授を務め、昭和37年第三内科教授に就任した。医学部卒業後赤堀四郎研究室に出入りし生化学の基礎を持つ山村は内科学教室では研究を重視していった。病気の原因を解明し治療法を見つけるには基礎の研究が欠かせない。山村は「夢見て行い考えて祈る」という言葉を医局員に送った。ロマンを持ち実現のため努力し、考え反省し、あとは結果を天に祈る。山村のこの言葉は多くの医局員の心の支えとなった。
山村は今日、阪大の「中興の祖」と称される。免疫学を導入確立した学問的業績ばかりでなく、第三内科教授から昭和42年48歳の若さで阪大医学部長に推され、時あたかも学園紛争で医学部が危機に瀕していた時期に対処された。第三内科教室でも民主的運営をはかるため教室会議が設置され、総務、診療、研究、教育の4委員会がつくられた。これらは現在も機能している。昭和51年教室員の協力にて南山堂から全4巻からなる内科学教科書「新内科学」を完成。昭和54年には第11代阪大総長に就任、組織としての第三内科および阪大を活性化させ、幅広い活躍をみせた。たとえば山村が第三内科主任教授だった昭和37年から55年の間、千葉大学を皮切りに徳島大学、熊本大学、愛媛大学、富山医科薬科大学、九州大学、佐賀医科大学など全国の大学に相次ぎ教授を送り出し、阪大第三内科の名を高めた。総長となってからは「阪大をバイオテクノロジーのメッカにしよう」と構想し、昭和57年「細胞工学センター」を設立。昭和50年代に入って、遺伝子組み換えをはじめとするバイオ技術が発展し、今後の医学はバイオを軸に展開すると考えたのである。初代センター長には後に文化勲章を受けた岡田善雄が就任。松原謙一、谷口維紹らを招いた。当時、これだけのスタッフを揃えることができたのは、山村の熱意と幅広い人脈に負うところが大きい。第三内科門下からも、医学部長、阪大総長と、山村と同じ道を進む岸本忠三が教授として参加した。その後、大阪医学校創立来112年間住み慣れた大阪市中之島の医学部と附属病院の吹田市への移転に奔走した。
日本免疫学会、日本アレルギー学会、日本癌学会、日本結核病学会などの会長、日本内科学会会頭などを歴任、昭和58年には第5回国際免疫学会議の会長も務めた。学問的業績では、昭和35年に朝日賞、60年には日本学士院賞、61年に学士院会員、63年には文化功労者。平成2年6月10日、72歳で逝去。
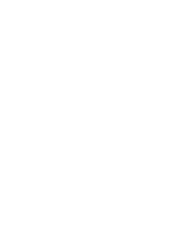
岸本進
第三内科 第四代教授
在任期間:昭和56年~平成元年
岸本進は昭和3年大阪に生まれた。昭和28年阪大医学部卒、翌年第三内科に入局。昭和37年~39年米国ピッツバーグ大学留学後、そのライフワークである「加齢と免疫不全」の研究を本格的に進め、昭和49年には熊本大学医学部第二内科教授に就任。岸本は血液学の権威としても知られ、在任中は血液学中心の同内科に免疫学を導入し、基礎研究の重要性を熟知していて、さらに発展させた。
昭和56年、学長となった山村の後任教授として熊本大学から母校に帰任し、「臨床と研究は共に内科学教室の車の両輪である」をモットーに、第三内科の臨床の充実に力を尽くした。研究を重視した山村時代には「三内」は「診(み)ない」と華々しい研究を妬まれて揶揄されることもあった(実際は、当然、診療もきっちりとなされていたが)。佐多、今村と基礎研究畑の教授が続いた後、堂野前という臨床の人材が就任し、また研究を重視した山村の後に臨床の充実に尽くす岸本が就任したのは歴史の配材であろうか。岸本は教室に血液学研究室を新たに創設し、第三内科を名実ともに臨床総合内科として確立した。そして、血液学研究の中で、57年、58年にかけて阪大初の骨髄移植に成功して以降、第三内科は骨髄移植を阪大の中心となって行うこととなった。当時、白血病は化学療法が限界に達し、不治の病とされていた。そこで米国に2人の医局員を派遣し、精力的に研究を進めた成果が阪大初の骨髄移植に結びついた。全身放射線照射や超大量化学療法で白血病細胞を叩き、無菌室内で安全に他人の造血細胞を骨髄に定着させるためには非常に高度な医療技術を必要とし、臨床医学の本質を問われるものであった。
研究面においてベッドサイドの問題を分子レベル、遺伝子レベルに掘り下げて、独創性のある世界に通じる研究に発展させることに力をつくし、もともとの専門分野の免疫学や血液学だけでなく種々の分野で数多くのすぐれた研究を生んだ。また臨床研究にありがちなその場かぎりの短編小説的問題解決に陥ることを戒め、長編大河小説的な研究を怠らないよう厳しく指導した。
岸本はその厳格さと生真面目さから、少し近寄り難く思われがちであったが、打ち解けると気さくな面も持っていた。夏の暑い日に吹き出る汗をハンカチで拭いながら真剣な眼差しで回診していた姿が医局員の胸に今でも残っている。医局員の結婚式で、新郎新婦の生い立ちを暗記してすらすら紹介する記憶力には皆驚いたものである。
退官後、大阪府立羽曳野病院(現、大阪はびきの医療センター)院長。
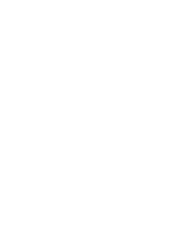
岸本忠三
第三内科 第五代教授
在任期間:平成3年~平成10年
岸本忠三は昭和14年大阪府富田林市に生まれた。昭和39年阪大医学部卒業、学生時代に元第三内科教授の山村雄一との出会いがあった。自分の体を守るはずの免疫が自分の体を攻撃してしまう「自己免疫疾患」という病気についての講義に感銘し、生涯を免疫学の研究に捧げることになった。卒業後山村のいる第三内科へ入局。その後ジョンズホプキンス大学石坂公成の下へ留学し、抗体産生を誘導する分子の研究に取り組んだ。昭和57年に山村によって新設された「細胞工学センター」の教授になり、インターロイキン6 (IL-6)という免疫細胞の情報伝達分子を解明、これが世界の免疫学会に反響を呼び起こした。平成3年出身教室である第三内科の教授に就任。
Bリンパ球を刺激する分子として研究されていたIL-6は、肝臓では急性期蛋白質を作らせ病気等で炎症が起きたときの異変に対処し、さらに血液や骨、心臓の領域でも働いていることが判明した。その後、IL-6受容体、共通信号伝達分子gp130、下流の転写因子STAT3、信号抑制分子SOCS1の発見など、岸本率いる教室はIL-6をモデルに世界のサイトカイン研究の先端を独走して行った。さらにキャッスルマン氏病や関節リウマチの患部では大量のIL-6が分泌され病態に関与していることを解明。IL-6は生体内での「多様性」とともに多くの炎症性疾患にも関与していたのである。1998年米国の科学情報研究所は、生命科学分野の1990年以降8年間の論文引用件数のランキングで岸本は世界第8位、免疫学分野ではトップであることを報告。論文の引用回数が多いということは、それだけ貢献度が高いことを意味する。
岸本の下には細胞工学センター時代から多くの俊才が集まった。「大阪弁で廊下まで響く嵐のようなお叱り」を受けた教室員も多いが、その中からその後論文被引用回数世界一に輝く審良静男をはじめとする世界に誇る日本の学者を多く輩出している。また、内科出身であることから、長年の研究成果を臨床に結びつけ、日本の製薬会社とともに抗IL-6受容体抗体を開発し、キャッスマン氏病や関節リウマチなどの治療薬(トシリズマブ)として導入、難治性炎症疾患の患者さんが寛解する事実を非常に喜んだ。
平成2年文化功労者、4年には恩賜賞・日本学士院賞、10年に文化勲章を受賞。この間、阪大医学部長、平成9年には医学部の一教室から今村荒男(第5代)、山村雄一(第11代)に次ぐ3人目の総長として第14代阪大総長に就任した。平成21年、第三内科出身の平野俊夫(第17代阪大総長)とともに日本人で初めてクラフォード賞を受賞、学者として多くの輝かしい栄誉を与えられている。阪大総長退官後も阪大に残り研究を続けている。
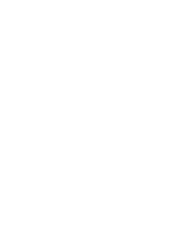
川瀬一郎
第三内科 第六代教授,呼吸器・免疫アレルギー内科 初代教授
在任期間:平成13年~平成22年
川瀬一郎は昭和22年滋賀県八日市市に生まれた。昭和46年阪大医学部卒業、当時山村が教授を務めていた第三内科に入局、国立がんセンター病院肺腫瘍内科での勤務(昭和48~53年)を命じられ肺癌診療の道を歩むようになる。大学の壁を越えて設立されたがんセンターの方式は当時まだ珍しく、活気と競争、緊張感にあふれていたという。昭和55~57年米国フレッドハッチンソン癌研究センター基礎免疫部門留学、昭和57年阪大第三内科に戻り、肺癌の診療、癌免疫の研究に取り組んだ。平成4年講師、6年大阪府立羽曳野病院(現、大阪はびきの医療センター)肺腫瘍内科部長として転出したが、平成13年出身教室に教授として呼び戻された。
川瀬は臨床一筋に歩んできたが、癌の免疫療法で学位を取っている。第三内科山村の開発した癌免疫賦活剤N-CWSに川瀬の作成した抗腫瘍モノクロナル抗体を併用すると治療効果が増強されるということを証明し、癌に対する抗体依存性細胞障害(ADCC)の有効性を見事に立証している。阪大講師就任後は、附属病院が中之島から吹田地区移転の際に臓器別診療科別再編に努め、新病院では病棟・外来から講座名は消して診療科名で統一した。羽曳野病院時代は進行肺癌の在宅医療を厚労省と幾度も交渉の末に実現し、緩和医療の充実は現在も引き継がれ伝説となっている。
第三内科教授在任中は、大学独立法人化、内科系科再編、新臨床研修制度など、大学医局を取り巻く環境が大きく変わった時期であったが、教室は川瀬の明るい性格で乗り切ることになる。平成16年度より2年間内科系科長として診療科別講座再編の中心的な役割を果たした。これまで総合内科として発展してきた第三内科は平成17年に呼吸器と免疫アレルギーを担当する内科として編成されたが、他科に異動となった旧第三内科教室員に対しては細かな気遣いを示していた。附属病院においては、診療看護倫理委員会および保健医療福祉ネットワークを設立し、終末期医療に関する阪大病院コンセンサスの策定、病診・病病連携の推進に貢献した。平成19年度からは、副病院長として労務管理、リスク管理、医療クオリティーを担当。特に医療事故は阪大病院の特性として重症例でのトラブルが多く、また終末期医療の問題など幅の広い内容のため猛烈に忙しい日々であったが、患者側の人たちと話し合う機会を幾度となく設け、真摯な姿勢でお互い納得できるかたちでおさめた。阪大病院が円滑に運営されている裏では、川瀬の人柄が頼りにされていたのである。
川瀬は教授として多忙な中でも、毎週研修医向けに胸部レントゲン読影指導の時間をもうけた。また、呼吸器内科の講義枠のほとんどを担当し、大阪弁でジョークを交えてまず笑わせ、学生の気を引いた後、臨床経験に基づいた重要点を押さえながらの講義は楽しくわかりやすいと人気があった。こうした川瀬の明るくエネルギッシュな人柄は学生には親しみやすく、彼らを引きつける魅力があった。川瀬が山村に憧れて第三内科へ入局したように、今度は川瀬を慕って医学生が集まって来たのである。川瀬は何事も決断が早く、明確な指示を医局員に与える一方、医局のカーペットの埃を一番に拾うなど細やかな心遣いにも溢れていた。
平成22年、大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター(現、大阪はびきの医療センター)に戻り院長に就任。