大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器・免疫内科学
Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, The University of Osaka
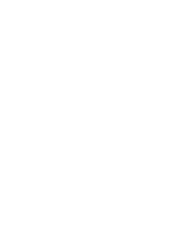
| 2000年3月 | 大阪教育大学教育学部附属高等学校天王寺校舎 卒業 |
|---|---|
| 2007年3月 | 大阪大学医学部医学科 卒業 |
| 2008年4月 | NTT西日本大阪病院(現:大阪警察病院) 初期臨床研修医 |
| 2010年4月 | NTT西日本大阪病院(現:大阪警察病院) 膠原病・リウマチ科 医員 |
| 2012年4月 | 大阪大学医学部附属病院 免疫アレルギー内科 医員 |
| 2013年4月 | 大阪大学大学院医学系研究科 入学 |
| 2017年3月 | 大阪大学大学院医学系研究科 修了(同年6月 学位取得) |
| 2017年4月 | 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学 助教 |
| 2020年10月 | ハーバード大学医学部 Brigham & Women's hospital Research fellow |
| 2021年10月 | 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学 助教 |
| 2024年10月 | 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学 講師(~現在) |
| 2025年4月 | 大阪大学医学部附属病院 免疫内科 科長・病院教授(~現在) |
<日本内科学会>
認定内科医・総合内科専門医・指導医・JMECCインストラクター・Young physicians committee 委員
<日本リウマチ学会>
評議員・専門医・指導医・登録ソノグラファー・J-STAR(Japanese Scientists to Advance Rheumatology)委員・J-STAR-IR(International Relationship)副委員長
<日本アレルギー学会>
専門医・指導医
<アジア太平洋リウマチ学会(APLAR)>
Education Committee Member/ Young Rheumatologists Education Chairperson
<日本免疫学会>
評議員
<日本炎症・再生医学会>
評議員・次世代リーダー育成委員会(FLY-IR)委員
<日本臨床免疫学会>
学術・認定医委員会・ヒトデータ共同研究小委員会・倫理委員会
<その他>
臨床研修指導医・日本救急医学会ICLSインストラクター
| 2024年10月 | JST創発的研究支援事業 創発PI |
|---|---|
| 2024年4月 | 第68回日本リウマチ学会総会 International Workshop Award |
| 2023年12月 | APLAR 2023 Travel Award on JCR |
| 2023年7月 | 第44回日本炎症・再生医学会 優秀演題賞 |
| 2022年4月 | 宇部興産学術振興財団 学術奨励賞 |
| 2022年4月 | 日本アレルギー学会 サノフィ優秀論文賞 |
| 2021年4月 | 日本学術振興会 海外特別研究員 |
| 2020年11月 | 令和2年度 大阪大学賞(若手教員部門) |
| 2020年8月 | 令和2年度 日本リウマチ学会奨励賞 |
| 2020年2月 | 研究成果の新聞掲載(産経新聞、日本経済新聞、読売新聞等) |
| 2019年12月 | 第3回先進医薬研究振興財団研究報告会 令和元年度最優秀若手研究者 |
| 2018年11月 | 第5回日本リウマチ学会BRC 次世代リーダーセッション講演 |
| 2017年11月 | 第4回日本リウマチ学会BRC 優秀演題賞 |
| 2017年7月 | 第38回日本炎症・再生医学会 優秀演題賞 |
| 2017年7月 | 第32回自己免疫研究会 最優秀演題賞 |
| 2017年4月 | 第61回日本リウマチ学会総会 International Workshop Award |
| 2017年3月 | 研究成果の新聞掲載(毎日新聞、読売新聞、朝日新聞等) |
| 2016年11月 | 第13回IWAA Award of exceptional abstract and presentation |
私は大阪大学医学部在学時、病院実習で母親と同じ年代の全身性強皮症の患者さんと出会った事をきっかけに、このような難病を診療できる医師になりたいと思い免疫内科を志しました。NTT西日本大阪病院(現:大阪警察病院に併合)での研修を通して免疫内科臨床の素晴らしさを教わった後、母校である大阪大学に戻り、免疫疾患の診療に携わっています。
私は常々、免疫疾患の診療は、エビデンス(知見)・イマジネーション(想像)・インフォームドコンセント(説明と同意)の三本柱で成り立っていると考えています。まず、医師は正確な試験デザインと統計に基づいた最新の知見を勉強し、把握する事が出発点です。その上で、目の前の患者さんにどのような病態が生じているのかを考え、時にチームで議論し想像する事が大切です。免疫疾患は多種多様かつ臓器横断的であり、縦割りの分類基準やガイドラインを適応するのみでは太刀打ち出来ないケースが多くある一方で、想像だけで突っ走ってしまっては的外れで時代錯誤な医療になってしまいます。エビデンスとイマジネーションをうまく掛け合わせて患者さんごとの最適解を求めなければなりません。
そして、私が最も重要視しているのがインフォームドコンセントです。免疫の病気は長年に渡り患者さんを悩ませる疾患が多いため、現在の病状はどうなのか、主治医はどのように考えているのかを説明し、納得していただくことが重要です。目に見えない「免疫の異常」を整理し、いかにわかりやすく患者さんに伝え治療を構築できるかが、免疫内科医の腕の見せどころであると考えます。限られた診療時間の中で患者さんや御家族が素直な気持ちを表出し、互いの意図を汲み取りやすい会話の雰囲気作りも大切にしています。これらの三本柱をバランスよく取り入れたオーダーメイドの治療こそが、多彩な病態に患者さんと共に立ち向かう術だと信じています。
また、免疫疾患の多くは慢性の経過を辿りますが、内科医として急変時の対応は常に迅速に出来なければならないと考えています。そういった気持ちから、日本救急医学会ICLSインストラクター、日本内科学会JMECCインストラクターの資格を取得し、講習会等で内科救急対応を指導しながら自身の研鑽も行うことをライフワークとしています。
難治性の免疫疾患の病態について、顆粒球(好中球や好酸球)活性化の原因究明や治療の研究を行っております。その中で、セマフォリン分子に代表される免疫ガイダンス因子が好中球の活性を制御するブレーキ役として働き、このブレーキが外れてしまうことが好中球の暴走を引き起こしANCA関連血管炎の発症に関与している事を発見、学位論文として報告しました(Nishide M, et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2017)。これを端緒として免疫ガイダンス分子群と疾患との関連にさらに興味を持ち、熊ノ郷淳先生との連名で総説を発表(Nishide M, Kumanogoh A. Nature Reviews Rheumatology 2018)、耳鼻科の先生と共に難治性アレルギー疾患である好酸球性副鼻腔炎とセマフォリン分子に関する研究成果を発表しました(Tsuda T, Nishide M, et al. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2020)。
2020年よりハーバード大学に留学する機会をいただき、好中球表面のFcγレセプターを介した自己抗体の取り込みや活性化制御の研究に従事しました。ボストンの学際的で自由な雰囲気に魅了され、素晴らしい留学経験を得ることができました。大阪大学に戻ってからは、ANCAによる好中球細胞死のメカニズムについて、接着因子との関連を新たに報告し(Lelliott PM, Nishide M, et al. ImmunoHorizons 2022)、それを生かした新しい動物モデルの構築・治療の研究を行っています。
また、免疫疾患患者さんからいただいた臨床検体を用いたシングルセル解析に取り組んでおります。患者さんと向き合う中で生じた疑問を多層的オミクス解析とベッドサイドの臨床情報の融合により追求し、ANCA関連血管炎の単球プロファイルに基づいた疾患層別化(Nishide M, et al. Nature Communications 2023)、ANCA関連血管炎にみられるユニークな活性化好中球集団の発見(Nishide M, et al. Nature Communications in press)、全身性強皮症の障害臓器多様性を形作る一端の解明(Shimagami H, , , Nishide M. Nature Communications in press)などの成果を報告してきました。免疫の病気を知り、患者さんを知る強みをシングルセルデータに投影しベッドサイドへ還元する「個の細胞から個の患者へ」という研究コンセプトで2024年度JST創発的研究支援事業に採択いただき、その重要性を自ら世界に向けて発信しています(Nishide M, et al. Nature Reviews Immunology 2024)。
私は専攻医時代に熊ノ郷淳先生に出会ったことで研究に興味を持ち、30歳を過ぎて初めて研究の世界に飛び込みました。当教室には私と同じく臨床医の経験を積んでから研究に触れる大学院生が多く在籍しています。また、医学生・研修医・専攻医としてご活躍中の方にも今後そのようなキャリアを考えている先生が多くいらっしゃると思います。そのような方々に研究の楽しさを伝え、自らの経験に基づいた身近なアドバイスをしてあげられる存在でありたいと思っています。
(英文:筆頭著者および責任著者)
(英文:共著者(抜粋))
|
Cell 2024 |
|---|---|
|
Neuron 2024 |
|
The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2024 |
|
The EMBO Journal 2023 |
|
Science Advances 2023 |
|
New England Journal of Medicine 2022 (Collaborators) |
|
The Journal of Immunology 2021 |
|
Nature Communications 2021 |
|
Nature Immunology 2018 |
|
Annals of the Rheumatic Diseases 2018 |
|
The Journal of Immunology 2018 |
|
The Journal of Immunology 2017 |
|
Nature Communications 2016 |
|
The Journal of Immunology 2015 |
|
Arthritis & Rheumatology 2015 |
(和文:筆頭著者)
(主要学術集会における招待講演:決定分を含む)
|
国際神経免疫学会 シンポジウム(日本・神奈川) |
|---|---|
|
アジア太平洋リウマチ学会 シンポジウム(日本・福岡) |
|
日本炎症再生医学会 教育講演(日本・京都) |
|
日本腎臓学会 シンポジウム(日本・神奈川) |
|
日本内科学会 生涯教育講演会(日本・北海道) |
|
日本内科学会 ことはじめ講演会(日本・大阪) |
|
日本リウマチ学会総会 シンポジウム・教育研修講演(日本・福岡) |
|
American College of Rheumatology Convergence(米国・ワシントンDC) |
|
日本炎症再生医学会 シンポジウム(日本・福岡) |
|
Federation of Clinical Immunology Societies(米国・サンフランシスコ) |
|
日本リウマチ学会総会 特別シンポジウム(日本・兵庫) |
|
日本内科学会総会 シンポジウム(日本・東京) |
|
日本臨床免疫学会 シンポジウム(日本・東京) |